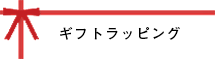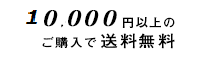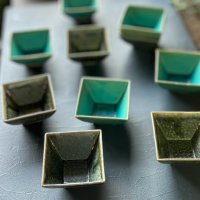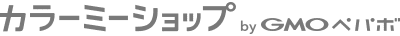~お気に入りのうつわを
少しでも長く気持ちよく
使って頂くために~
食器を大きく分類すると、
「磁器」と「陶器」に分けられます。
実店舗でも、
まずお客様に、どちらをお好みがお聞きしてから
商品をおすすめしています。
メーカーでは様々な土を使用する為、
一見区別がつかないものや、
磁器を陶器っぽく作っているものもありますが、
ざっくりと説明すると・・・
【磁器】

『陶石』と呼ばれる石の粉に粘土を混ぜたものが原料。
薄手で表面がツルツルしていてツヤがあり、美しい。
吸水性がなく、
比較的丈夫で扱いやすく普段使いに適している。
電子レンジ・食洗機の使用可。
【陶器】
主に自然界で取れる粘土が原料。
特に土物(※)は、
厚手でひとつひとつに素朴さや味があり、
手造りの醍醐味を感じる。
(貫入だけでなく、
色むらやピンホール・鉄粉なども器の個性としてとらえています)
吸水性があり、
磁器に比べると衝撃に弱いが、
使う度に変化していく過程も楽しめる。
(※蔵ショップでは特に、
土目が粗くて貫入が入った器を『土物』と紹介しています)
それぞれ特徴がある為、
取扱いにも注意が必要ですが、
難しく考えずに楽しんでいきましょうね。
●ご使用前にしていただきたい事

・器の底を、
指でなぞってみてください。
発送前に確認致しますが、
もしざらつきが残っていましたら、
テーブルをキズつけてしまうので、
サンドペーパーや砥石で、
こすってください。
・磁器は中性洗剤で洗って頂き、
そのままお使いください。
・陶器 特に吸水性がある器(粉引・貫入)は、
ご使用前に目止めをした方が汚れがつきにくくなります。
又、ご使用時に水にくぐらせて、
あらかじめ水を含ませることで、
汚れが染み込みにくくなります。
●目止めの手順について
(粉引・貫入・素焼きの器は特におすすめします)

1)うつわが全て隠れる大きさのお鍋に、
うつわがかぶるくらいの米のとぎ汁を入れます。
2)火にかけ、沸騰したら弱火で20分~30分煮沸します。
3)火を止め、そのままの状態で冷まします。
冷めたら器を取り出しきれいに洗います。
4)水気を拭き取り、
しっかりと乾燥させます。
※水分を含ませただけで、
陶器の表面にシミのように見えるものが
現れる場合がありますが、
しっかりと乾かしていただくと、消えます。
●陶器(土物)のご使用上の注意
・陶器も磁器同様に、
電子レンジ・食洗機をお使いいただけますが、
器同士がぶつかりあわないように気をつけてください。
・土物は電子レンジ・食洗機の使用を
オススメできません。
が、あたため程度のなら問題ないと思います。
ただし電子レンジのご使用を繰り返すことで
ヒビの原因になる場合もあります。
(金彩・銀彩の器は電子レンジ使用不可)
・長時間、色やにおいの強いものを、
入れたままにしないでください。
・ご使用後はすぐに洗い、
しっかり乾燥させてください。
乾燥不足は、
カビ・変色・においの原因になります。
・急冷・急加熱をさけてください。
器が割れることばあります。
・洗剤を直接かけると染み込んでしまい、
温かいものを入れた時に、
洗剤のにおいがする場合があります。
●貫入について
『貫入(かんにゅう)』とは、
うつわの表面に施された
ヒビのような模様のことです。
器が焼かれた後の冷えていく過程で、
土と釉薬の収縮度の違いによっておこる現象です。
使用前から見える場合と、
使っているうちに現れてくる場合とあります。
使っているうちに、
茶渋や珈琲が、
貫入に染み込んで変化していくのも
「味」としてとらえ、
変化を楽しんでくださいね。
●もし、着色やにおいがついてしまったら・・・
・汚れた部分に塩または重曹をふりかけ、
湿らせたスポンジでこする。
・においをとる場合は、
重曹またはキッチン用漂白剤を
溶かした水に浸す。
・鍋にお酢大さじ2~3杯または、
茶殻ひとつまみ入れた水に器を浸し、
火にかけて煮ると消臭効果があります。
(熱湯に器を入れると割れる危険があります。
必ず水から煮てください。)
●最後に・・・~ずぼらな私編~
陶器(土物)の扱いには色々と注意点があり、
めんどくさいなぁ~と思ってしまいますよね。
ここまで説明しておいて何ですが、
ずぼらな私は、
「目止め処理」なんてほぼやっていません。(笑)
電子レンジも食洗機もふつうに使っています。
もちろん、
粉引の器などシミができているのもあります。
(怒られちゃいますね・・・)
シミができたら漂白剤に浸し、
とれなかったら「味」とする。(笑)
貫入は表情として変化を楽しむ。
ただ、少しだけ気を付けている事は、
『使う前に水にくぐらせる。』
『長時間食物を入れたままにしない。』
こんな感じで肩の力を抜いて器を楽しんいただけたらな~と思います。